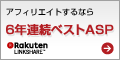ミュージカル作品のジャズ・アルバムでは、『マイ・フェア・レディ』(シェリー・マン&ヒズ・フレンズ)につづくのが、『ウエスト・サイド・ストーリー』ということで、そんないくつかの作品も聴いてみたくなり…。
1962年リリースのオスカー・ピーターソンのアルバムもよく知られていますが、1957年舞台初演から近く、1961年の映画化前のものをちょっと調べてみました。
このミュージカル作品の大ヒットの所以は、20世紀アメリカ・ニューヨーク版「ロミオとジュリエット」といえるストーリーであると同時にレナード・バーンスタイン手がける音楽であるわけですが、この時期のカヴァーもすばらしいものばかりですね。
これまた知らずだったのですけど、アンドレ・プレヴィンの他も、カヴァーしてたのは、じぶんのテイストにあうなぁと他の作品でも気に入っているウエスト・コースト・ジャズの方々。まだアルバム通しで聴いてはいないのですけど、よさそうなものばかりですね。近日入手でのメモとして、それぞれのアルバムから試聴で気に入ったナンバーなどを。<アンドレ・プレヴィン Andre Previn>
まずは、アンドレ・プレヴィン&ヒズ・パルズの『West Side Story 』から。
このアルバム、アンドレ・プレヴィン(Andre Previn)がメインの名義ですが、「ヒズ・パルズ」ということでの友情メンバーは、シェリー・マン(Shelly Manne)とレッド・ミッチェル(Red Mitchell)。1959年リリース。
Andre Previn and His Pals Shelly Manne & Red Mitchell:America(1959)
シェリー・マンのドラムス効いてますね。そしてつくづく、プレヴィンのコードセンスは苦みばしっていて、きりっとスタイリッシュ。
<カル・ジェイダー Cal Tjader>
つづいて、この方ヴァージョンもあったのかぁ、というのが、カル・ジェイダー(Cal Tjader)。
ファンタジー・レーベル(Fantasy Records )で、アレンジとピアノは、クレア・フィッシャー(Clare Fischer)。シェリー・マン(Shelly Manne)とレッド・ミッチェル(Red Mitchell)は、この作品にも参加してるのですね。1960年リリース。
Cal Tjader:Cool(1960)
ヴィブラの音色がまさにクールで、涼しげ、且つかっこよしです。
<デイブ・ブルーベック Dave Brubeck>
そして、デイブ・ブルーベック(Dave Brubeck)もカヴァーしてたのですね。
サックスはもちろんのポール・デスモンドで。いま出ているCDでのヴァージョンは『ウエスト・サイド・ストーリー』からのカヴァーが全曲ではないようですが、ジャケットもですけど、アルバムの構成もバリエーションがありですね(バーンスタイン・オーケストラのものももともとはいっしょに収録されていたのだとか)。1960年リリース。(Paul Desmond)
さておき
Dave Brubeck Quartet :Maria(1960)
ならではなリズム変化、それでありながら、流れるような軽さのサウンド展開がすてきですね。デスモンドのサックスも歌ってます。
(投稿:日本 2012年10月31日、ハワイ 10月30日)